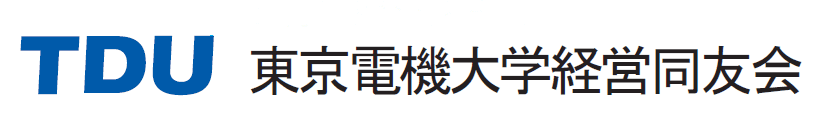もっと女性の笑顔を増やしたい!
こんにちは、長妻明美です。私は、2016年に工学部機械工学科先端機械コースを卒業し、2018年に大学院工学研究科機械工学専攻先端機械コースを修了しました。大学院では、三井和幸教授(以下、三井先生)の医用精密工学研究室(以下、三井研究室)に所属し、卒業後は研究室の共同研究先に就職。現在も研究開発に携わっています。
仕事では、先端技術に触れることが多い上に、初めて訪れる土地に出張することも多く、常に新しい経験を得られる刺激的な日々を過ごしています。また、仕事以外にも、大学時代に始めたカメラをはじめ、着付けや縫製、刺繍、読書、美味しいものを食べたり作ったりすることなど、多彩な趣味を楽しんでいます。今回は、学生時代の体験と、私の想いをお話ししたいと思います。
研究室での開発を通して発見したこと
研究室を決める際、企業と共同でとモノを開発することで得られるものがあると考え、企業との共同研究に積極的な三井研究室を選びました。三井先生は、常に挑戦する機会を与えてくださり、学部生の頃から企業との打ち合わせや出張など、貴重な経験を積むことができました。
それまで、機械工学を学ぶ理由は、面白いから、不思議だから、という単純なものでした。しかし、大好きな機械工学を通して、人々の役に立つことを考えたり、作ったりすることに、更なる面白さを感じるようになったのです。
フランス研修で学んだ大切なこと
大学3年生の春休みに約1週間の短期フランス研修に参加し、東京電機大学の姉妹校であるENSMM(ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE MÉCANIQUE ET DES MICROTECHNIQUESフランス国立高等精密機械工学大学院大学)などを訪れました。語学だけの研修とは異なり、英語による機械やプログラミングの実習、フランスの企業訪問といった内容の濃いプログラムでした。
滞在中は学生寮に宿泊し、現地の学生との交流、企業や工場の見学、ENSMMのある城下町ブザンソンやパリなど観光もしました。ブザンソンは機械式時計発祥の地であり、ENSMMの時計部の学生に機械式時計の仕組みを教わりながら、実際に分解と組み立てを体験させてもらいました。
 左:ある日のENSMMの学食。ほとんどの食事に大量の芋料理が含まれていて、毎食驚いていました学食では肉料理か魚料理を選べましたが、どちらも芋料理では?と面白かったです。
左:ある日のENSMMの学食。ほとんどの食事に大量の芋料理が含まれていて、毎食驚いていました学食では肉料理か魚料理を選べましたが、どちらも芋料理では?と面白かったです。
右:チョコレート屋さんのショーウインドウブザンソン。当時の日本ではあまり見かけない形や色のチョコレートは斬新で驚きました。
順調に研修内容をこなす中、『事件』が起きてしまいました。宿泊していたホテルにiPadを置き忘れるという大失態をしてしまったのです。しかも気づいたのはパリに向かうTGV(フランスの新幹線)に乗車中。もう頭の中は真っ白でパニック状態!すぐに研修の指導教員である大西謙吾先生(以下、大西先生)へ伝え、車中からホテルに電話をかけてもらい、iPadを探してもらうようお願いをしてもらったり、ENSMMやTDU国際センターからもホテルに連絡してもらうよう、お願いしてくださったりと手を尽くしてくださいました。
結局、iPadは見つかりませんでした。唯一の連絡手段だったiPadを紛失したために、研修メンバーと予定していた夕食の時間に寝過ごして行けなくなった時も連絡ができず生息不明状態になったのはもちろんのこと、家族からの連絡にも返信できず、とにかく周囲を心配させてしまいました。
携帯電話も腕時計も持っていなかった私に、大西先生は「目覚まし時計にでも使いなさい」と、ご自身のタブレットを研修期間中貸してくださったのです。
さらに、追い打ちをかけるかのように、日本から持って行ったドライヤーをコンセントに直接差し込んで、発火させてしまうなど、現地では数々のトラブルを起こしてしまい、参加した他のメンバーからは“Legend(レジェンド)”と呼ばれる始末・・・
これらの出来事により、大西先生をはじめ研修を共にしたメンバー、その他、ENSMMや東京電機大学の職員の皆様に、多大なるご心配とご迷惑をおかけしてしまいました。たくさんの方に助けていただき感謝の気持ちで一杯です。
このiPadの紛失をはじめ、一連のトラブルを通じて学んだことは、まず自分自身を見失わないことが重要であるということでした。
 左:お惣菜屋さんのショーウインドウ ブザンソン。こんな素敵なショーケースから選べるなんて良いな!
左:お惣菜屋さんのショーウインドウ ブザンソン。こんな素敵なショーケースから選べるなんて良いな!
右:街中にメリーゴーランド ブザンソン。いつでもメリーゴーランドに乗られるって夢のようだな。
フランスの大学の研究環境に学ぶ
フランスの大学や企業を見て強く刺激を受けたことがあります。それは、大学の研究室では研究に必要な機材の多くが企業から支給されているということです。大学も企業と競争するレベルで研究を行う一方、企業は将来に向けて共同開発を進めるために、大学へ機材を提供する関係性がある程度成り立っていました。
また、フランスは学費が安く、学生は高度な研究に関わるチャンスが得られやすいのです。日本のように高い授業料を払った人だけが高度な技術を学べる環境とは異なります。私の場合、大学の入学金から授業料、そして大学院にかかる費用すべてを貸付の奨学金を利用していたため、フランスでの学びの環境には憧れるものがありました。
さらに、博士号取得者への対応もフランスと日本では大きく異なります。フランスの場合、大学や企業からの支援がある程度充実しており、博士課程の学生にも将来に向けた投資ということで雇用契約が発生し給与ももらえます。卒業後も支援先の企業にそのまま就職ということも少なくないようです(もちろん企業として欲しい人材像とマッチすれば)。
日本の場合、博士号を持っていても研究内容を生かすことを含めハードルは高く、就職時の面接等で「博士課程なんて取ってどうするの?当社では修士も博士も給与は変わらないよ」と言われるような状況です。これが今の日本の実態なのかと、愕然としたことはいうまでもなく・・・
女子学生のキャンパスライフ充実のために〜電大ガールズでの活動
少し時間を戻して、在学中に関わった“電大ガールズ(D-girls)”について触れたいと思います。東京電機大学の女子学生がイベント企画などを通じて情報交換やネットワークを広げたりすることを目的に2014年に発足しました。私はこの発足に携わり、1年目から様々なイベントを企画し、継続するための基盤づくりを行いました。
たとえば、女子学生限定運動会の開催をはじめ、大学全体を対象としたクリスマスパーティー、オープンキャンパスでの女子学生と保護者向け相談ブースの運営、新入生向けのオリエンテーリング、地域の小学生向けの理科教室、季刊誌の制作、各種取材対応など様々です。
これらを実現するにあたり、大学との交渉や、他の活動団体、学生への協力依頼など、学びながらこれだけのことができたことに自分でも驚いています。おかげでコミュニケーション力も高められました。
どの活動も多くの方に喜んでもらい、優秀な先輩方や頼もしい大学職員の皆様のおかげで、私自身も活躍の機会を得ることができました。今後も、電機大には女子学生の心の拠り所となるような場所が存在し続けてほしいと願っています。
 左:電大ガールズ集合写真。最前列右から3番目が著者です
左:電大ガールズ集合写真。最前列右から3番目が著者です
右:電大ガールズクリスマスパーティー。電大ガールズではじめて開催したクリスマスパーティーの様子です
最後に、女性が抱える問題を知って欲しい!
私には、女性特有の悩みを軽減・解決したいという思いがあります。複数の女性技術者から、時短勤務をすることで元の給与の約6割に減ってしまったという話を聞いたことが一つのきっかけでもあるのですが、男性や社会、年上の方々と関わる中で、女性が不利に感じることや、そのような状況に置かれないような環境とは?を意識するようになりました。
例えば、女性技術者の生涯賃金が男性技術者に比べて低いことが挙げられます。全体として見ても、令和3年の男性一般労働者の給与水準を100としたとき、女性一般労働者の給与水準は75.2という調査結果も※。
※内閣府男女共同参画局データより。
女性が出産前後に長期休業を取り、保育園の送り迎えや数年間にわたる時短勤務を余儀なくされることや、介護サービスへの送り迎え、自宅での介護のための時短勤務や休業も女性が担うことがまだまだ多く、積極的にサポートする男性は増えてはいるものの、この傾向はまだまだ変わりにくいと考えています。
ある女性社員は「そんなに給与を維持したいなら、たくさん残業して働いて、そのお金でベビーシッターでも雇えばいい」と人事から言われたそうです。仕事をこなす力があってもこんなことがまだ起きている。。。とショックを隠しきれません。
そういった事例はまだまだ氷山の一角に過ぎず、不利な状況で働く女性社員のために、女性が就労する上でこれまで理解されていなかったことへの理解を広げ、お互いにフォローしあえる環境を創りたいと考えています。先輩方にも、頑張る女性たちの現状を通じ、改善のためにお力添えいただけたら、私たちにとって大きな励ましになります。そのためには、先輩方のお力添えが必要なのです。
最後に、この場をお借りして、恩師である三井和幸先生、東京電機大学教職員の皆様、研究に協力してくださった学外の方々、一緒に学んだ仲間のみなさん、育ててくれた親戚や家族に、心から感謝の気持ちをお伝えします。様々な体験をさせてくださり、本当にありがとうございました。また、このような機会を提供してくださった校友会の皆様に、感謝申し上げます。
最後まで読んでいただきありがとうございます。私が書いた内容は、あくまで私個人の現状における見解であり、今後も働き続けることで考え方が変わっていくかもしれません。先輩方には私自身の成長を見守っていただけたら嬉しいです。

2016年卒業
工学部機械工学科先端機械コース
2018年修了
大学院工学研究科機械工学専攻先端機械コース
長妻 明美