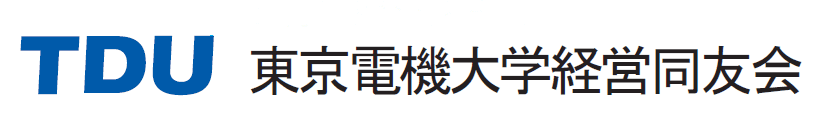電気設備のプロとして安全を守り、人との縁の大切さ想う
はじめに
みなさん、こんにちは。私は平成7年(1995年)に工学部電気工学科を卒業した櫻井達史です。
私が入学したときは千葉ニュータウンキャンパス(以下、千葉NT)ができて2年目でした。1年生のときは千葉NT、2年から4年生までは神田錦町*1に通っていました。卒業後、神田へ行く機会がなかなかなく、そうこうしているうち神田錦町の校舎は無くなってしまいましたが、神田錦町の校舎を知っている人と、7号館だ11号館だと話すと大変懐かしく当時を思い出します。
卒業後は、電気工事会社に約10年、メーカーに約20年従事しました。現在は個人事業主として自家用電気工作物の保安管理業務を行っています。途中、電気関連以外の仕事もしていましたが、さすがにもう転職する気持ちはなく、最後は電気関連の仕事で終わらせようかと考えています。
*1 神田錦町、錦町の校舎:神田キャンパスのこと。平成24年に東京千住キャンパスへ移転。跡地はKANDA SQUARE<神田スクエア>となっている。
自家用電気工作物の保安管理とは?
現在の仕事は、個人事業主として自家用電気工作物の保安管理を行っています。「自家用電気工作物(以下、電気設備)」とは『電力会社から600Ⅴを超える電圧で受電し、電気を使用する設備』のことを言います。一般用電気工作物よりも大規模で、高電圧の設備が多いため、安全管理がより重要になります。
これらの電気設備は、その設置者が自己責任において保安規程を作成し、さらに電気主任技術者を選任して、電気の保安を確保することが法律で義務付けられています。私が行っていることは、お客さんが保有する電気設備をお客さんに代わって保守点検を受託する業務、ということになります。
電気設備の点検内容には、毎月の月次点検と、年1回の年次点検があります。月次点検は通電状態での点検となり、ひとりで行っているため特に感電事故を起こさないように注意しながら点検や測定を行います。次に年次点検では、電気設備を停電させて、各種リレー試験、高低圧絶縁抵抗測定、接地抵抗測定など、通電時にはできない点検や測定を行い、電機設備に異常がないか詳細に確認を行います。
緊張と工夫を伴う仕事
点検作業は慎重に行いますが、点検が終了し復電準備に入るときは更に細かな目配りが求められます。電気設備内に工具などの点検用備品を置き忘れたりすると、復電のときに大事故を起こす恐れがあるからです。
そのため、使用する点検用備品の「員数管理」もまた重要な作業となります。停電や復電作業は、何度やっても何年経験しても緊張するものです。同じような業務を担う卒業生はたくさんいらっしゃると思いますが、同じような感覚をお持ちなのではないでしょうか。
またお客様の電気設備は、屋外に設置されていることが多いことから点検業務は天候に左右されます。暑い日は空調服を着て汗を拭いながら、寒い日は防寒着を着て震えながら作業を行います。雨が降ると作業ができなくなることが多く、その場合にはやむなく延期したりもします。
梅雨や台風時期になると毎日天気予報とにらめっこしながら業務への影響度をチェックします。1~2週間先の天気予報を見ながら調整を行うのですが、台風が発生すると予報も急に変わり、計画が崩れてしまうこともしばしば・・・ですので、台風時期は特にハラハラします。
挑戦と学び。個人事業主としてすべてを自分で
個人事業主となると当たり前ですが、すべての業務を自分で行う必要があります。この「すべて」とは、保安管理業務以外に資材などの発注や経理業務、雑務など、会社員時代には各々の業務担当者に任せておけば良かった様々な業務を指します。現在はそれらを一人で行っています。特に経理業務は今までにやったことがなく1から勉強です。最初、何からどう行えばよいのかも分かりませんでした。
ただ昔と違って、現代はネット環境が整っているので、ネットの中の情報を参考にしながら作業を進めていきました。どうせなら経理関係の資格も取得してみようと考え、この歳になって新たな分野の勉強を行っています。
また、個人事業主は作業時間も自分で決めることができるので、巷で言われている「働き方改革」なんてものは皆無です。良くも悪くも、働きたいときに働き、休みたいときに休む、といった感じでしょうか。そのため、会社員の頃よりも仕事と休息の境をしっかり持つようにし、メリハリを付けることに気を付けています。この辺りは会社員時代の経験が生かされていると思います。
支え合う、人の縁の大切さ深く考える
何事もひとりで行う、とは言いましたが、やはり周囲の人の助けを借りないと成り立たない仕事もあります。特に年次点検など停復電作業を行う際は、安全面や停電時間も限られていることから、周りの人の助けを借りて持ちつ持たれつな関係を持ちながら複数人で行います。
こういう時に思うことは、人とのつながりの大切さでしょうか。自身の感覚ですが、会社員時代より人との関係性を重要視するようになりました。そういう年代になったせいなのかもしれません。若い頃には微塵も思っていませんでしたが、この頃、人との縁を深く考えるようになりました。
えっ!こんなことあるの!~ 校友会に繋がる驚きの再会
さて、『人との縁』とは面白いもので、校友会神奈川県支部に入ったのもまさしく『縁』からでした。個人事業主となって、会社員時代より比較的自分の時間を持てるようになり、ある飲み会に参加したところ、現在の校友会神奈川県支部長の平山さん*2と出会いました。
この平山さん、実は電機大卒業後に就職した電気工事会社の上司でした。電気工事会社を辞めてから30年以上、連絡も取り合っていなかったので、飲み会で「知っている人に似ているな」とは思っていましたが、まさかその本人とは思わず、驚きました!
平山さんも自分のことを覚えていてくださり、この再会が校友会に入るきっかけとなったのです。『人との縁』というのは恐ろしくもあり、面白くもあり不思議なものです。
*2 神奈川県支部長 平山 文雄氏
神奈川県支部の情報 https://www.tduaa.or.jp/branch/location/kanagawa/
最後に:縁を構築する、縁を大切に生きる
人と人はどこで繋がりを持つようになるか分かりません。
学生時代の友人、会社に入ってからの上司部下、同僚など色々な繋がりがあります。今更になってよく感じますが、人間ひとりでは世の中を渡っていくことはなかなか難しいことかと思います。周りに相談できる人がいることは、その人の強みではないでしょうか。
ぜひ、周りの人との縁を構築し、そしてその縁を大事にしながら人生を歩んでいきましょう。思いもよらないところで、縁が繋がることがあるかもしれませんよ!
平成7年(1995年)
工学部電気工学科卒
櫻井達史